独身なのに祝うばかり…取りっぱなし感にモヤモヤ
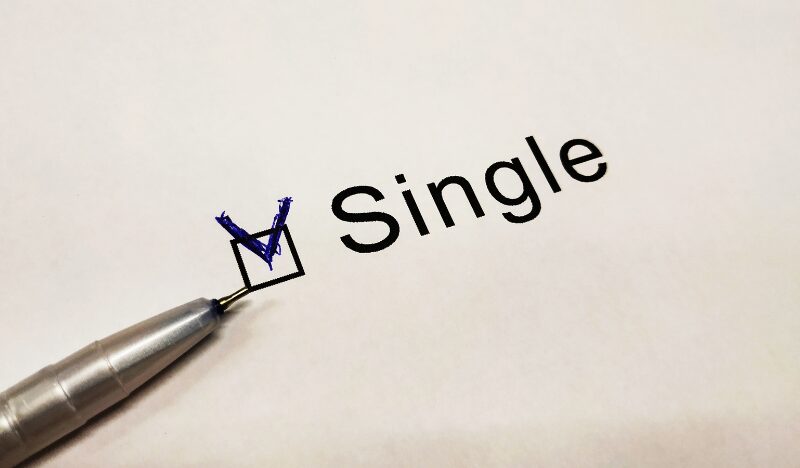
ずっと祝福する側に立たされて、「いつか回収できるのかな…」とため息が出る気持ち、す結婚や出産といった人生の節目に際し、職場で贈る「お祝い」。
これは祝福の気持ちを表す文化である一方で、独身者、とくに女性の間では「贈るばかり」で恩恵を受ける機会がほとんどないという現実が広がっている。東京都内で働く38歳の女性は、これまで同僚の結婚式や出産祝いなどで「50万円を軽く超える出費をした」と語る。それに加えて、同僚が産休・育休に入る際には業務のしわ寄せを一手に引き受けることも多く、「お祝いにお金を出し、業務の負担も担う」存在になっているのが実態だ。
こうした状況に対し、女性たちは「祝いたくないわけではない」としつつも、制度や社会的配慮の乏しさに不満を抱いている。現在の福利厚生制度は子育てや介護など特定のライフイベントを対象とした支援が手厚く設けられているが、独身で健康な人には利用の余地すら与えられていない。仮に制度が整っていても、その「入口」に立てないことで、構造的に損をしていると感じるケースが多い。
さらに、子育てや教育支援の拡充も、独身者にとっては一種の格差として映ることがある。2026年度から始まる「子ども・子育て支援金」の導入では、すべての医療保険加入者から保険料を上乗せで徴収しつつ、支給対象は子どものいる世帯に限られる。こうした制度の仕組みに対して「独身税ではないか」と批判が集まる背景には、「自分たちは納めるばかりで、見返りがない」という単身者特有の苦しさがある。
都の子育て政策においても、0~18歳の子どもへの毎月5,000円の支給や無痛分娩費用の助成、高校無償化など、子育て世帯に手厚い支援が次々に発表されている。一方で、「なぜ子育ては社会で支えるという文脈になり、独身者への配慮はないのか」「出産は自己選択なのに、なぜ公共予算で手厚く支援されるのか」といった声も上がっている。
とくに都市部では、独身者が年々増加しているにもかかわらず、政策設計や社会保障制度は依然として「夫婦+子ども」という旧来モデルを前提に作られており、「声なき声」が政策議論に反映されにくい。外資系企業に勤める43歳の女性は、教育無償化の動きを見て「なぜ他人の子どもの学費を自分が負担するのか」という疑問を感じるとし、「子育て世帯の負担を減らすのは理解できるが、独身者にも何らかの配慮があってしかるべきだ」と語る。
本来、少子化対策や育児支援は重要な政策課題であり、社会全体で子育てを支える必要性はある。しかし、それと同時に、支える側である独身者や子どものいない層が、精神的・経済的に孤立していないかにも目を向けるべき時期にきているのではないだろうか。結婚・出産を経て恩恵を受けられる社会構造のなかで、“ずっと祝う側”として立ち続ける独身者の声を、これからの制度設計にどう組み込んでいくのかが問われている。
記事のまとめ▼
- 独身女性の実情:「結婚祝いや出産祝いを贈る金額が累計で50万円超に達した」という声が出ている
- 職場の暗黙ルール:同僚の結婚式へ「参加しないわけにはいかない」というプレッシャーが存在し、心理的負担も大きい
- 業務負担のしわ寄せ:祝福する側が出費だけでなく、同僚の休暇や育休の穴埋めまで担うケースが多い
- 子育て支援制度とのギャップ:育児助成や手当は独身者には恩恵がなく、「結婚・子育て優先」の仕組みに疑問が集中している
- 制度設計の偏り:扶養控除や子ども手当などが既婚子育て世帯を手厚く支援する一方、独身者は負担するだけの構造になりやすく、制度上の「冷遇感」が拭えない
参照:Yahoo!ニュース

お祝いでお金を出すのは全然いいんだけど、正直「またか…」ってなると、だんだん心から祝う気持ちが薄れてくるんだよね~。

最初は純粋に「おめでとう!」って思えるけど、何度も続くと「また出費か…」って気持ちが勝っちゃう時あるよね。
お祝い事は嬉しいけど、負担が積もると気持ちの余裕まで奪われていく感じ…。
子育て支援や各種補助金はあっても、独身者向けの支援って本当に少ない。
税金も社会保険料も同じように払ってるのに、使える制度が限られてて、なんだか報われない気持ちになるときあるよ。










